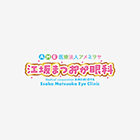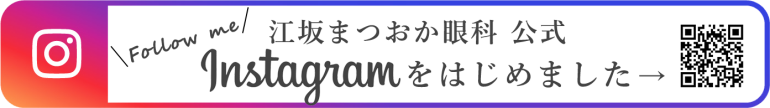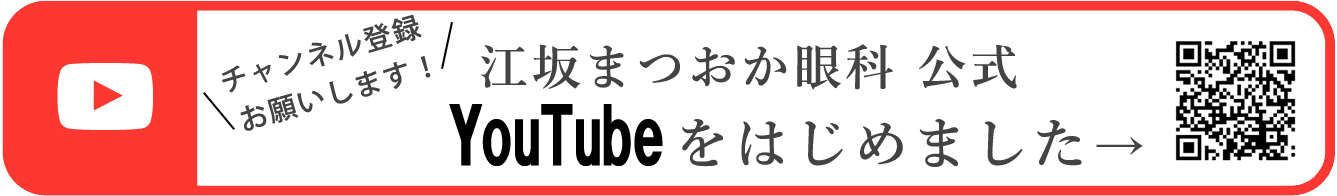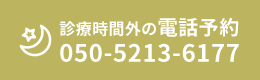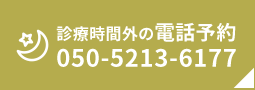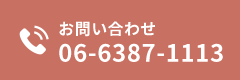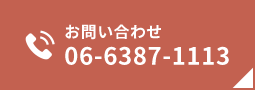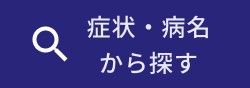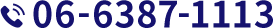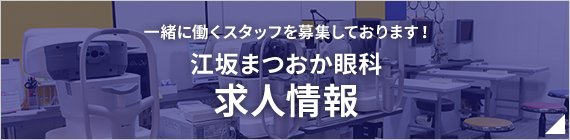黄砂が健康に及ぼす影響について

目次
黄砂とは?
黄砂(こうさ)とは、中国内陸部の砂漠地帯(ゴビ砂漠、タクラマカン砂漠、黄土高原など)から飛来する微細な砂粒のことです。春先に強い風が吹くことで砂塵が巻き上げられ、日本を含む東アジア各地へと広がります。
黄砂の発生と増加の背景
黄砂は昔から自然現象として存在していましたが、近年では以下のような理由で頻度や影響が増しています。
-
- 砂漠化の進行:森林伐採や過放牧、気候変動の影響で、中国内陸部の乾燥化が進み、より多くの砂が巻き上げられるようになった。
- 産業活動の影響:中国の工業化によって大気汚染物質(PM2.5など)が増え、これらが黄砂と結びつくことで有害性が高まる。
- 気象条件の変化:エルニーニョ現象や偏西風の変動により、黄砂が日本に飛来しやすくなる年がある。
- 特に2000年代以降、黄砂の飛来が多くなったとされており、日本でも春先(3月~5月)を中心に注意が必要になっています。
黄砂の季節性と気象との関係
-
- 春に多い理由:冬から春にかけて中国内陸部では乾燥した状態が続き、強い風(偏西風)が吹くため、砂が舞い上がりやすくなります。
- 気温との関係:春先はまだ寒暖差が大きいため、気圧配置が不安定になりやすく、黄砂を運ぶ風が強まる傾向があります。
- 梅雨時期や夏以降は少なくなる理由:梅雨入りすると雨によって大気中の黄砂が洗い流されるため、飛散量が減少します。また、夏は気流の影響で黄砂が東アジアに到達しにくくなります。
黄砂の成分と人体への影響
黄砂には単なる砂粒だけでなく、以下のような物質が含まれています。
-
- 鉱物粒子(石英、長石、粘土など):自然由来の成分で、気管支に入ると炎症を引き起こすことがある。
- 重金属(鉛、カドミウム、ヒ素など):工業汚染によって黄砂に付着し、体内に取り込まれると健康被害を引き起こす可能性がある。
- 細菌・カビ・ウイルス:長距離を移動する間に細菌や真菌(カビ)、ウイルスが付着し、感染症のリスクを高める。
- 硫酸塩や硝酸塩:大気汚染物質と結びつき、PM2.5のように肺へ深く入り込みやすくなる。
黄砂が人体に及ぼす影響
-
呼吸器系への影響
-
- 喘息や気管支炎の悪化
- 喉の痛み、咳、鼻炎
- 呼吸困難や肺炎のリスク増加
-
目への影響
-
- 結膜炎(目の充血、かゆみ、異物感)
- ドライアイの悪化
-
皮膚への影響
-
- アトピー性皮膚炎の悪化
- かゆみや湿疹の発生
-
心血管系への影響
-
- 血圧の上昇や動脈硬化の促進
- 心筋梗塞や脳卒中のリスク増加
-
全身症状
-
- 頭痛、倦怠感
- 免疫力の低下
- アレルギー反応(花粉症の悪化など)
黄砂対策
-
- 外出時の対策
●マスク(N95マスクなど高性能フィルター付きのもの)を着用
●眼鏡やゴーグルを使い目を保護
●長袖・帽子を着用し、肌の露出を避ける - 室内対策
●空気清浄機(HEPAフィルター搭載)を使用
●窓やドアを閉め、外気の侵入を防ぐ
●室内の湿度を適度に保ち、乾燥を防ぐ - 生活習慣の工夫
●帰宅後はすぐに洗顔・うがいをする
●衣服をよくはたいてから室内に入る
●バランスの良い食事や十分な睡眠で免疫力を維持
- 外出時の対策
まとめ
黄砂は単なる砂埃ではなく、重金属や有害物質を含むため、呼吸器系・皮膚・目・心血管系に悪影響を及ぼすことがあります。特に春先は黄砂の飛来が増えるため、外出時の防護や室内環境の管理が重要です。
最新の黄砂情報を確認し、適切な対策を講じることで、健康被害を最小限に抑えましょう。